―死んでも何も変わらない
緩和ケア病棟で、「死ぬのが恐い」という男性に、「死んでも何も変わりませんよ」と応じたら、「相談にのって欲しい」と返されたことがあります。死の恐怖は、自己が無になるという漠然とした前提にあるのではないか。わたしが、「死んでも何も変わりませんよ」と言ったのは、ソクラテスが念頭にあった。ソクラテスは、死を場合分けして評価する。もし、死が無への回帰であり、熟睡のような気持ちの良いものであれば、死に忌むべきものは何一つない。それとは反対に、魂が不滅だとすれば、死は、魂が肉体の束縛から解放される至福以外のなにものでもない。つまり、意識がなくなって、自己が無になるとすれば、その無になった自己を確認する手立てはないのだから、熟睡のように「何も変わらない」。そうではなく、魂としての自己は死後も継続するのであれば、これまた「何も変わらない」。
人間の精神にとり死は存在しないという思想もあります。ドイツ観念論者フィヒテは、生物的な死は、その背後に隠されていた生が高揚し、横溢する端緒だと、われわれの死の理解とは正反対の理解を提示します。
―どのように生きたら満足して死ねるか
どのように生きたら満足して死ねるのだろうか。このテーマを深めるには、人間というものについて、生物学、哲学、文学など幅広くさまざまな視点から人間理解を深めることがまず求められます。他方で、個人的な経験の掘り下げも必要になります。これまでの人生を振り返って、自分はどういうときに悦びを味わい、どういうときに充実感を感じたのか。満足感を得たのは、どういう経験からか。反対に、どういうことに後悔しているのかなど、人生にまつわる個人的な経験を想起し、ひとつひとつを慎重に吟味してみる。そのようなプロセスを経て、自分なりに、満足して死ねる生の方向生を見定めることができるかもしれません。
―健全な精神が病をいやす
19世紀にアメリカで流行した精神治療運動は、人間の「健全な心」が病を癒す力があるという理念に立っている。健全な心とは、取り越し苦労や恐怖、悲観と言った精神状態を跳ね除ける、勇気や信頼、希望という性質である。あるいは、本当の自己を身体ではなく、神に由来する魂なのだと自覚する人間観そのものが、病を癒す力をもつ。この運動は実際に病気に苦しむ多くの人を救った。現代でも偽薬効果は認められ、心の持ち方だけで免疫力を高めることは証明されている。とはいえ、病癒しに関しては、さまざまな詐欺事例もあるのも事実である。この精神治療運動は、健全な精神を勧奨することで、病にたち向かう力を与えた。すると、死に臨んでも、心のあり方が焦点化されるのだろうか。
―生と死
生物的にみれば、生と死は対立しているのではなく、生には死が書き込まれていると考える方が自然。では、精神的な意味で、生が熟して死にいたるとはどういうことか。
老人になると、死を意識し始め、去り行く者として、残された一日一日を悔いのないように充実して生きようとする。あるいは多くの知人、友人を見送り、生きていることが、何か奇蹟的な出来事のように感じ始める。そこからさらに進んで、自分の死後からこの世を眺める視点にさえわれわれは立つことができる。すると、一日一日が貴重でかけがえのない経験に思え、小さな日々の出来事が感慨深く心に刻まれる。十分に生きた果ての死は、充実した満足感に満たされるのかもしれない。この自分の死後から自分の生を眺める死生観が、死という根に支えられた生命を生きることを初めて可能にすると私は思う。
―死は自己意識の消失か?
一般に、われわれは死が意識の消失であり、意識的自己は無になると考える。たしかに、アルコールや薬物を摂取すれば、脳の神経系に作用し、意識は変化する。あるいは、脳に損傷をうければ、意識や行動に異変が起こるのは疑えない。また身体に傷を受ければ、自分の身体が痛いと意識する。また疾病によって、精神的な気力まで衰えるのは経験的事実である。そのため、意識の消失は自己意識の消滅という脳神経科学が前提とする仮定が真理のように受け入られている。しかし、それは「不当仮定の虚偽」かもしれない。われわれは根拠のあいまいな科学主義の前提を信じて、死を恐怖するが、それこそ実証的な態度とはいえない。死後もわれわれの生が継続するという思想はソクラテス以来、形を変えて連綿と存続している。近年は、臨死体験において、脳死に近い状態で、清明な意識の存続があったとする事例研究が蓄積されてきている。
臨死体験は脳内の現象だとする説もあるが、見た光景が客観的事実と合致している事例もある。それは、どのように説明できるのだろうか。
神秘体験は、われわれの合理主義的概念を越え出たものだが、われわれが永遠の存在で、生きた宇宙のすべてとつながっているという洞察を与えることもある。ウイリアム・ジェイムズによれば、われわれの合理的意識は目覚めているときの意識の特殊型にすぎず、この意識の回りに、それとはまったく異なった潜在的な形態の意識がある。そのために、神秘体験は起こると解釈している。われわわれの自己意識は宇宙に開いている。
―自己とは何か?
自己とは自明なものではなく、なぞだとも言える。われわれが不安や怖れを感じるのは、自己意識のそこに潜む無意識の広がりが分らないことにもよる。自己を出来事として捉える考え方がある。たとえば、「パソコンで文章を書いている」、その自己を意識するとき、自己は現れる。他方で、パソコンで文章を書くことに没頭しているときは、自己意識はなくなっている。それは、自己意識の消失ではなく、自己は潜在的に存続していると考えるべきだろう。意識したときに、自己は戻るのだから。すると、自分に起こった出来事や経験が自己意識の源泉と考えることができる。ここから展開すると、自己とは自分の経験した出来事の束であり、その束に一貫した筋道をつければ、自分の人生のヒストーリー(歴史)となる。
ジェイムスによれば、われわれの自己には、宇宙ではたらいている、広く高い部分の萌芽が含まれている。その萌芽は、われわれの成長への悦びや、理想を求める衝動、究極的な意味へのあこがれなどに示唆されている。われわれの自己は自己を越えた存在から生きる意味を汲み取っているともいえる。このような哲学の系譜を現代まで辿り、死を越える生の人間観を探求していきたい。
―量子力学からみた自己意識
量子の重ね合わせの状態が、観測するとひとつに定まるという量子力学の難題がある。フォン・ノイマンは、観測を量子系と観測者の抽象的自我に分割する。量子系には物質である観測機器、観測者の神経系も包含される。それらは数学的に記述できるためである。抽象的自我は、この宇宙の物質から独立していることになる。
弦理論、超弦理論、M理論は、素粒子の元は振動する弦と考える。これらの理論は、高次元の世界を想定しているが、四次元より高度な次元はミクロに折り畳まれていて、目には見えない。神秘体験は、この世界を超え出た体験でもあり、高次元世界との接触として位置づけられる。明晰夢などもまた、この高次世界との接触なのかもしれない。 このように考えると、次元を超えた人間の意識の存続も考えられうるのではないか。
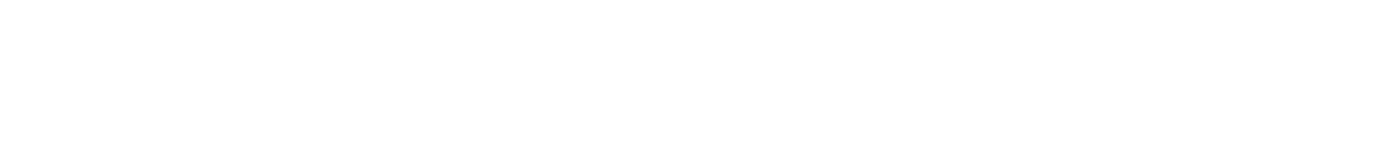



コメント