緩和ケア病棟で、「死ぬのが怖い」と率直に告白されるのを何度か聞いた。われわれは、死をどのようにイメージしているのだろう。
一般には意識がなくなって、身体が消滅し、自分が永久にこの世から消え去るものとして死を把握している。しかし、離人症の人は、「自分がなくなってしまった」「自分が実感として感じられない」と訴える。それと並行して、ものの実在感もなくなる。これは、一般の人も疲れたときなどかかる神経症である。たとえば、目の前に花があるとする。離人症の人は、その花という物体、その色、形は認識する。しかし、花を美しいものとして感じる自己はうしなっている。自分がないということは自分のがかかわる世界の実在感も同時に失う。つまり、科学的な中立的客観的対象としての世界は、生気も実在感もないことになる。問題となっているのは、自分の実践的関与を促す主観的な世界の出現が失われているということである。
木村敏によれば、われわれが日常的に経験している自己は、身体という「もの」ではない。目の前の物体を実在として、いきいきとして感じとる自己が問題なのであり、その自己は「もの」ではなく、たえず生成する「こと」としての自己である。
人と人との関係においても、相手の身体という「もの」ではなく、相手の表情や所作から心情の動きという「こと」を読み取って交流している。このように、自己を「こと」という視点からみると、自己とは何かを理解する糸口が見えてくる。
身体は細胞が絶えず入れかわって、動的平衡を維持している。それと同様に、自己も非自己と出会って、自己を自覚する。つまり、自己とは生成する運動である。われわわれが自己と考えているものは、自己ではないのかもしれない。
親しい人と対話すると感情が活気付くのは、感情が交換されるからであり、その意味では感情は人と人とのあいだに、身体を超えて広がっているように思える。われわれの日常生活においては、身体は媒体としてのスクリーンの幕のように意識にのぼらないが、痛みなどの不具合があると意識にのぼる。
ともかく、死に臨むとき、われわれは自己は身体だと狭く限定しがちになる。身体の痛みやだるさを感じながら寝ていると、身体の調子に意識が集中するようになる。そのため、にわかに身体と自分とを同一視することになる。この身体と自己とを同一視することから解放されれば、死はそのトゲを抜かれることだろう。
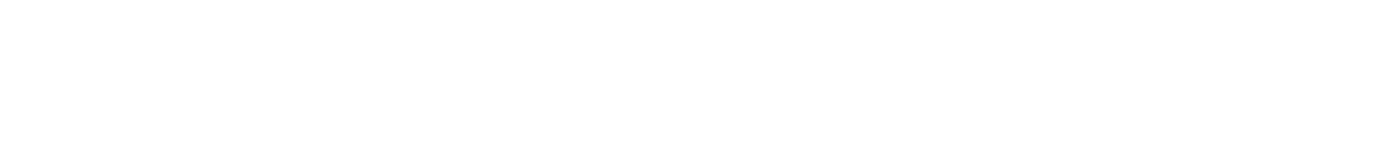



コメント