ブログ4
伴侶との死別
老齢になり、多くの葬儀に参列するようになった。葬儀会場で、冷静沈着を絵に描いたような人が伴侶の死に慟哭しているのを目にしたことがある。さびしさに伴う喪失感は、突然思いもかけないときに襲ってきて、その迫真性は自力ではコントロールできないことがある。それはなぜなのだろうか。ある患者さんは、「死ぬのはそれほど恐くないが、寂しいものだ」と言った。死にゆく人も別れのさびしさを感じているとするなら、亡くなった人と遺された人のさびしさが共鳴して、われわれに強く迫ってくると思われなくもない。とはいえ、高齢の人は自分もまもなく死者の列に加わると思えば、多少なりとも、そのさびしさは和らげられるのではないか。
その後、さまざまな人から配偶者との死別のつらさを聞くことになった。ある女性は、夫の不在がつらくて、月一回グリーフケアのグループに参加してなんとか平常心を保っているという。このさびしい空虚感と悲しみは時々忘れることはあるが、生きている限り消えることはないという。また別の女性が語ったこと。夫を見送った後に、どうしようもない空虚感とさびしさに襲われた。あるとき、この宇宙の広大さに比べれば、自分の悩みなどはとても小さな芥子粒のようなものだと気づき、抑うつ状態からすこし恢復したという。
若竹千佐子は、夫との死別を「体が引きちぎられるような悲しみ」と表現する。知人は、伴侶との死別は、「人生で最大最強の精神的打撃だった」と振り返る。
緩和ケア病棟で出会った九○代の男性は、退職後妻と日本中を旅行した。妻は俳句、自分は短歌が趣味だったという。妻亡き後、さびしさに耐えかねて、二人で旅行した場所を訪ね歩き、そこで、いやます寂寥を感じることになった。
結婚した半数の人はいずれ配偶者との死別を体験する宿命にあるのだから、その精神的打撃を覚悟すべきである。われわれは死ねば、意識がなくなり、自己の存在が消滅すると漠然と考えているが、そのような死の理解で、配偶者との死別や自分の死に対処できるのだろうか。ともかく、死別という悲嘆を通過することによって、結婚生活は完結するのだろう。それは、われわれの人生にとって、どのような意味をもつのだろうか。
伴侶との死別が、これまで味わったこともないような強い情動を引き起こすのは、意識的あるいは無意識的に相手との共同生活において広がっていた感情の不在が鮮烈に意識されるためだろう。だから、配偶者のように長期間にわたって親密な関係が形成され、その関係が自分の内面の本質的な部分にまで分かち難く浸透してきている場合には、死別は自分の心そのものが、持ち去られたように感じられるのではないか。逆に言えば、死別の悲嘆が自分の存在全体を揺るがすほどのものだったとしたら、親しい者との深い感情的交流が成立していた証しともなる。配偶者との死別は、個人としての自己の根底が何に支えられていたのかを明らかにすると同時に、亡き人の自分に対する真実性も露わにする。
C.S.ルイスは、最愛の妻を亡くし、その不在を嘆いて、悲嘆にくれる。そのなかで、切実に求め続けたのが、亡くなった妻の「存在の確証」だった。あるとき「彼女の心がいっときわたし自身の心と相対した」経験が訪れる。その経験をとおして、ある種の「晴れ晴れとした親近感」が満たされた(.ルイス『悲しみをみつめて』102‐103頁)。
亡き人の「存在の確証」は、夢に現れるという体験でも起こる。夢にリアルな存在として亡くなった人が現れ、その存在が疑えない真実として感じ取られると、そのリアルな感覚は疑えない体験的真実として残存する。そして、このような体験から死別の悲嘆が実際に和らげられる。亡き人が存在し続けていることを切望するのは、人間関係の親密さの深まりそのものが、相互の不死を求めざるを得なくするともいえる。
柳田邦男は、親しい人の死を体験すると(二人称の死)、死後観が変わるという。確かに、多くの知人を見送ると、死後の世界が身近になってくる。亡くなった人が自己の内面に生き生きと働きかけてくるようになるからだ。故人の記憶の意図的想起だけではなく、思いもかけぬときに心の中から故人が語りかけてくる。故人のかつて言った言葉が、とつぜんよみがえっくることがある。これは、死者が生者に働きかけるという「存在の確証」ともいえるのではないか。この経験は、老齢になってはじめてわかってきたことだ。時間を長く共に過ごした親密な人は、無意識の中に生きているのだろうか。とはいえ、記憶やイメージのなかでの故人は、自分に都合のよいように変容されているのも確かだ。現実の人間は、記憶やイメージとは異なり、つねに異質な存在感を放っている。
配偶者や親しい人との死別が、底知れぬさびしさや慕わしさを感じさせるのは、彼らが自己の内面の一部になっているのに、それまで共有していた情緒が不在となるためである。しかし、内面化された相手の人格は失われることはなく、生きて心に語り続ける。新聞に掲載された短歌に、「白梅のかおり立つ道をドライブす 来たことあるねと亡き妻がいう」というものがあった。情景に触発された「来たことあるね」という妻の言葉は、妻の人格全体を立ちあげる。そこに死者のかっての言葉に触発された親密な感情的交流のリアリティが現出する。死者は記憶のなかにとどまっているのではなく、記憶に能動的に働きかけて、親近感を与えるのかもしれない。
われわれの生は、現在が過去に流れ去り、未来が現在に到来するという意識が開く時空の地平の中で営まれている。その時空は物理的時空間とは異なる。われわれの生きている時空間は、過去が実在し、ベルクソンのいうように、過去が現在にせり出してくる。亡き親しい人が自分の内面に生きて働きかけるという経験は、おそらく誰もが味わう普遍的なものだろう。
ここで、死別に伴う悲嘆と寂しさという強い情動は、ときに暴力的に迫ってくるように感じられることもある。悲嘆の圧倒的力は不安と怖れを引き起こす。それはなぜなのだろうか。
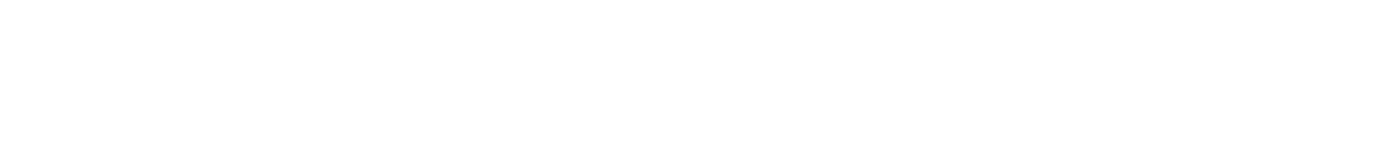


コメント